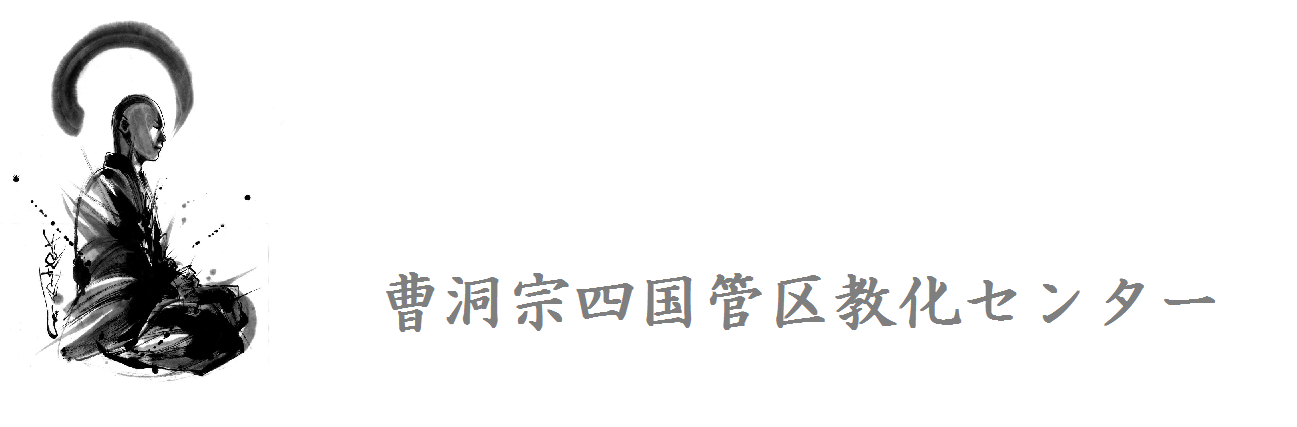法話:新着3
a:109 t:2 y:0
- 新着の法話
- 2024/05/11~20 六根清浄
- 2024/04/21~30 深い眼で
- 2024/04/11~20 あるがまま
- 2024/03/21~31 思いやる心
- 2024/01/21~31 手のぬくもりに
- 2024/01/11~20 鷺鶿(ろじ)雪に立つ
- 2023/12/21~31 願い事の前に
- 2023/12/11~20 愛語 ~思いやる心~
- 2023/11/21~30 解き放たれる~行雲流水~
- 2023/11/11~20 地球は大きな宝船
- 2023/10/21~31 喫茶喫飯
- 2023/09/21~30 禅的生活~学ぶはまねる
- 2023/08/21~31 自分の行いを顧みる
- 2023/08/11~20 不殺生戒
- 2023/07/21~31 許す心 思いやる心
- 2023/07/11~20 一期一会
- 2023/06/21~30 思いやり
- 2023/06/11~20 ええこと聞いたわぁ
- 2023/05/21~31 今なすべきことを
- 2023/05/11~20 布施の心を忘れずに
- 2023/04/21~30 他は是れ吾にあらず
- 2023/04/11~20 肌色のクレヨン
- 2023/03/11~20 こだわりを捨てる
- 2023/03/11~20 柔軟心
- 2023/02/21~28 相手の立場に立つ
- 2023/02/11~20 守る
- 2023/01/21~31 初志貫徹
- 2023/01/11~20 お正月の過ごし方
新着の法話
2024/05/11~20 六根清浄
講師:高知県 予岳寺 濱田道圓師
五月五日は二十四節季の立夏、新緑が眩しい初夏を迎え
ました。先日は徳島県の剣山で山開きが行われたそうで
す。私はそのニュースを聞いて、西日本最高峰の山、愛
媛県の石鎚山に登ったときの記憶が蘇ってきました。あ
れは夏の頃でした。いくつもの鎖を使って急な岩場を登
り、ようやく山頂にたどり着いた時の空気の冷ややかさ
と、達成感を今に思い出します。
さて、山登りの小休止が終わって立ち上がろうとすると
きもそうですが、重いものを持ち上げたり、立ち上がっ
たりするときに「どっこいしょ」と言うことがあります
よね。
この語源には諸説あるようですが、山岳信仰の修験者や
信者が山に登るときに「六根清浄」と唱えたことが由来
だとも言われています。つまり、「ろっこんしょうじょ
う」が「どっこいしょ」に変わっていったということで
すね。
六根とは、眼、耳、鼻、舌、体、そして心。つまり、色
や音、匂い、味、触感などの刺激を受け取る体の器官の
ことを意味しています。心は何かの刺激をきっかけにし
て過去を思い出したり、想像したりするもので、いわゆ
る直感もその一つといえましょう。これら六根は、自分
と他者の関りや、自分と他者を比較するときに重要な役
割を持っています。
私たちはとかく、自分と他者とを比較して、あの人より
も美しくなりたいとか、おしゃれをしたいとか、えらく
なりたいなどと思いがちです。それはそれで仕方のない
ことですが、気を付けていないと、それらの欲望に囚わ
れてしまいます。その結果、他者から妬まれたり、僻ま
れたり、ときには軽蔑されることもあるでしょう。
では、その六根で感じることを自分の欲望だけを満たす
ためや、自分だけが喜ぶためではなく、他者の笑顔のた
めに使ってみたらどうでしょうか?自分と他者がともに
気持ちよく過ごせるように、教室や職場をきれいにする、
笑顔を心がける、相手に優しい言葉をかける。そうされ
て不快に思う人はいないはずです。むしろ、感謝や労い
の気持ちが行き交い、穏やかな雰囲気になるのではない
でしょうか?自分自身と他者がともに笑顔になれる行い
が、新しい良い繋がりを生むことになります。
私たちが六根で「感じる」ということは、他者と六根で
「繋がっている」ということです。六根を欲望で曇らせ
ることなく、みんながお互いに気遣い合い、笑顔で過ご
せるよう、「六根清浄、どっこいしょ」を心がけたいも
のですね。
2024/04/21~30 深い眼で
講師:徳島県 城満寺 田村航也師
先日、先代の住職が昭和の終わりに記した文書が見つか
りました。その中には、お釈迦さまの弟子である阿難尊
者が、王様から多くの布衣を施された際に、その使い道
を問われる話が収められていました。
王様が「尊者はこのような多くの衣をどうされますか?」
と問うと、阿難尊者は「衣の破れた弟子たちに分け与え
ます」と答えました。そして王様が「その破れた衣はど
うされますか」と尋ねると、阿難尊者はこう答えました。
「破れた衣で床布を作ります。古くなれば、それを巻い
て枕の中身に、また古くなれば敷物に、さらに足拭き、
雑巾、最後は細かく裂いて壁の塗りこみに使います」。
王様は「お釈迦さまの弟子たちは、物の活用を善く心得
ておられる」と感心してその場を去ったというお話です。
このお話について先代の住職は、「悟りある人は無駄を
省き、生活を乱さず、自信を持って生きる」とコメント
しています。
先代住職は、ものを無駄にせず大切に使っていました。
倉庫の壁には、徳島で有名な海苔の丸箱がびっしりと並
べてあって、ネジやクギなどが細かく分類されて収納さ
れていました。段ボールにはぴったりとシワを伸ばした
レジ袋がいっぱいに積み重ねられていました。袋は経年
劣化で使えなくなっていましたが、先代の住職の心意気
はハッキリと伝わりました。
阿難尊者は王様から寄進された衣を弟子たちに分け与え、
その衣が使えなくなった後の使い方にまで心を配られま
した。先代住職は、いつだれが使っても良いようにと、
ネジや釘やレジ袋をきちんと整理して保管していました。
阿難尊者も先代住職も、目先のことに流されることなく、
それぞれのモノを大切に扱い、先々の使われ方や使う人
にまで心を配っていました。
翻って現代の私たちの生活はどうでしょうか?「便利」
という名の下に「使い捨て」のような単純で短絡的な思
考に馴らされ過ぎていないでしょうか?
世間に起きる事件、インターネット上でのいじめや中傷、
スマートフォン依存やゲーム中毒など、どれも豊かな想
像力や深い思考を欠いている傾向があるように思います。
インターネットの向こうには人がいます。ゲームは作り
手の世界観を超えることはありません。そして何より、
人は誰でも、私やあなたと同じ、心を持っているのです。
目の前の物事や周囲の人々を一歩立ち止まって深く見つ
め直しましょう。そうすれば、モノへの見方や使い方、
周囲の人との新たな関わり方が見えてくるはずです。
2024/04/11~20 あるがまま
講師:徳島県 城満寺 田村航也師
先日、お寺の境内に直径2mを超える大きな繭の球が5
つ、置かれました。この球は、1万匹ものお蚕さんを自
然な円運動でゆっくりと回転させながら作ったもので、
それを自然染色家の伊豆原さんが染めたものです。山の
ふもとでウグイスが鳴き合っているのどかな境内に突然、
5つの惑星が現れて、宇宙空間のような不思議さと静け
さを醸し出しました。
それと同時に、お蚕さんの繭から絹の布を織り、大きな
トンネルにしたものも展示されました。大人も子供もこ
のトンネルの中に入り込み、入り口の円形に切り取られ
た満開の桜を楽しみながら、そこに並べてあるいくつも
の小さな鐘の音を鳴らして耳を澄ませます。境内の宇宙
のような大空間の中に、誰もが落ち着けて楽しめる小空
間、小宇宙を作り出す仕掛けでした。
ところが、このトンネルを据え付けるのが思いのほか大
変なのでした。トンネルを吊るすためには、大きな支柱
を立てる必要がありました。さて、どうしたものかと考
えていた時に目に留まったのが、枯れかけた山桜の木で
した。
数年前から勢いがなくなり、花も少なくなったので、切
ろうかと言われていたのを、一つでも花が付くうちは生
かそうと、切らずにいた桜です。とうとう今年は花を一
つも付けず、ああもう切らねばなるまいかと残念に思っ
ていたのですが、そこでひらめいたのが、この山桜をト
ンネルの支柱にできないものか?ということでした。
大勢の人の助けを借りて、自然な色に染められた絹織り
のトンネルが山桜の枝に吊られました。「枯れ木に、花
が咲いた!」・・・誰もが、そう思いました。枯れ木に
花を、咲かせましょう。トンネルを吊った皆が、花咲か
じいさんになりました。死の世界に踏み出していた木を
生の世界に戻すことができたのでした。
私は「あるがままの世界の中では、生も死もなく、生や
死が尽きることもない」という『般若心経』の世界をそ
こに見ました。大自然の中では、新緑の若葉は秋に紅葉
し、冬には枯れ葉となります。けれども、散った葉は積
もり積もって腐葉土となり、新たな芽吹きの温床になり
ます。一枚の葉っぱの生と死は絶えず繋がっている。そ
れが大自然の姿であり、あるがままの世界です。
桜の木も死を乗り越えて支柱として生かされました。死
には価値がなく、目の前にある生だけに価値があるとい
う偏った見方をせず、あるがままに過ごしていくことが
最も大切なのだと般若心経は教えています。般若心経の
教えにしたがって、穏やかな毎日を過ごしていきたいも
のですね。
2024/03/21~31 思いやる心
講師:愛媛県 宗安寺 能仁洋一師
長い間一緒にいた大切な人が亡くなる前に『虫の知ら
せ』というものを耳にすることがありますが、実は私
も同じような体験をしたことがあります。それは、今
から20数年前のことです。
その日、私は修行道場での生活が二年目に入った、あ
る夏の日でした。私はその日、梵鐘などの鳴らし物を
用いて時間を知らせる鍾点という役目についておりま
した。お昼を知らせる鐘をつくために外に出て空を見
上げると、雲ひとつない真っ青な空が広がっていまし
た。鐘楼堂へ向かおうと歩き始めた時、何かが私の足
にスリスリと触れる感触がありました。その瞬間、私
は思わず「リキ?」と大きな声を出していました。
リキというのは、私が小学校一年生の時に家にやって
きた子犬の名前です。彼はいつも元気いっぱいで、私
が小学2年の夏に大きな野良犬に襲われそうになった
ときには、その身を挺して私を守ってくれたこともあ
りました。私がそばに立つと決まって、遊んでほしそ
うに頭を足に擦り付けてきて、そのふさふさの毛の感
触はとても心地よいものでした。
しかし、高校を卒業して県外の学校に進学してからは
半年に一回、修行生活に入ってからは一年に一回しか
会えなくなり、修行2年目の春に帰宅したときには、
リキはすっかり年老いていました。それでもリキは大
喜びで私を迎えてくれて、いつものように頭をスリス
リとこすりつけてくるのでした。短いお休みが過ぎ、
修行道場に戻る日、私はリキの頭をなでながら「また
帰ってくるからね、元気でおってよ」と声をかけて家
を出ました。
それから数か月後、あの夏の日の鍾点当番の日。私の
足にリキの頭の毛の感触が伝わってきたのです。それ
はまるでリキが挨拶をしにきたかのような感触でした。
私が小学校一年生からおよそ18年の歳月を一緒に過
ごしてきた大切な家族であるリキのことを『元気でい
るだろうか』と心から案じていたように、リキも私の
ことをそう想ってくれていたのかもしれません。
そんな不思議な出来事があった夏が終わり、秋が来て、
冬が過ぎ、三年目の春。お休みをいただいて家に帰る
とリキの姿はありませんでしいた。そうです、あの夏
にリキは旅立っていたのです。「どうして知らせてく
れなかったの?」と姉を問い詰めると、姉は「あなた
には伝えなくても分かっているような気がして…」と。
姉の言葉を聞いて「ああ、やっぱりあれは、リキのお
別れの挨拶だったのか」と、胸が熱くなったことが昨
日のように思い出されます。
このお話はけして、いわゆる不思議体験とか心霊現象
といった類のことをお伝えしようというものではあり
ません。おそらくは、年老いたリキのことが私の心に
引っかかっていて、着物の裾が当たった感触がリキの
毛の感触と錯覚しただけのことだったのだと思います。
ただ、この一連の体験から私は、家族との絆が時間や
距離を超えて存在するということ、互いの幸せを願い
合うことの大切さを学びました。
修証義というお経に「同事というは不違なり」という
言葉があります。これは、「相手と同じ立場に立ち、
同じ気持ちで考え、ともに喜び、ともに悲しみ、寄り
添って生きよ」という教えです。思えば、リキと私も、
お互いを思いやり、心を寄り添わせながら過ごした1
8年でしたし、リキとの思い出は今も色あせることは
ありません。
そうした思いは家族だけに限らず、すべての生きとし
生けるものに向けていかねばなりませんね。願わくば、
お互いが心を通わせ、お互いの幸せを願いながら過ご
せる世界が訪れますように。憎しみや争いのない、穏
やかな日々を過ごすことが出来ますように。
戻る***2024/03/11~21 勘定に入れず [#k0851224]
講師:愛媛県 宗安寺 能仁洋一師
私が住職をしているお寺では、お釈迦さまの御命日であ
る2月15日から春彼岸の3月末にかけて、涅槃図を本
堂の脇間にお掛け致しております。涅槃図とは、お亡く
なりになられたお釈迦さまを取り囲んで、大勢のお弟子
様方をはじめ、さまざまな動物たちまでもが、嘆き悲し
んでいる姿が描かれています。
今年も涅槃図をお掛けして手を合わせていましたら、絵
の中の犬を見つけ、子供の頃に飼っていたリキの事を思
い出しました。リキというのは、私が小学1年生の頃、
我が家にやって来た犬の名前です。来てすぐの頃は小さ
い体でおどおどしていましたが、中型犬ほどの体格にな
る頃には、やんちゃで悪戯ばかりするようになり「かわ
いい」と思う一方で「なんだ、こいつは!」と思うこと
もしばしばでした。
そんな折、ある出来事が起きました。友達の家に私とリ
キ。一人と一匹で遊びに行った帰りの山道での事です。
私たちの前に突然、大きな野良犬が現れたのです。こち
らに気づいたその大きな犬は、わずか数メートルの距離
で立ち止まると、低い唸り声をあげだしました。幼かっ
た私は恐怖のあまり体が凍り付き、その場で動けなくな
ってしまいました。と、その時です。傍にいたリキが私
とその犬の間に割って入り、自分のふた回り以上もあり
そうな大きな犬に唸り声をあげたかと思うと猛然と飛び
かかっていったのでした。
目の前で繰り広げられる二匹の戦いはほんの数分程であ
ったのかもしれませんが、私にはとても長い時間に感じ
られました。激闘の末、大きな犬は踵を返して走り去っ
ていきましたが、リキはその場でうずくまり動けなくな
ってしまいました。
リキに駆け寄った私は「リキ!大丈夫か?ありがとう!
ありがとう!」と頭を撫でながら何度も繰り返すばかり
でした。しばらく経ち、それでも立ち上がれそうにない
リキを、『今度は私が助けるんだ!絶対に家まで連れて
帰るんだ!』そう思って抱きかかえ、家まで歩いて帰り
ました。
いつもは抱きかかえられるのを嫌がるリキなのに、大人
しく抱きかかえられていたのを今も憶えています。それ
から数日が経ち、リキの怪我が癒える頃には、以前と比
べてぐっと信頼関係が強くなったように感じました。
修証義というお経の一節に『利行』という言葉がありま
す。利行とは、一言でいうと誰かを助けるということで
す。修証義では次のように教えています。『助けるとい
うことは、それが人であれ動物であれ、ただ無心に相手
のことを案じて行動を起こすことである。』と教えてい
ます。
リキが自分よりもはるかに大きい犬に向かっていった姿、
傷ついて動けなくなった姿を40年近く経った今も鮮明
に憶えています。おそらくリキは、私と一緒でなかった
ら尻尾をまいて退散していたはずです。でも、あのとき
のリキは幼い私を助けようとして、自分の命を顧みず果
敢に立ち向かってくれました。リキのことを単に自分の
家の飼い犬だ、言うことを聞かないやつだと、心のどこ
かで見下していた私だったにも拘わらずに・・。
そんなことを思い出しながら、私はあの時、リキから利
行の何たるか、「相手がだれであろうと、へつらうこと
なく、見下すこともなく、名誉や称賛などの損得を勘定
に入れずに行動することの大切さ」を教わったのだと、
今更ながら気づかされたのです。私たちは多くの命に囲
まれて、支え支えられという、ご縁の中で生きています。
そのご縁を大切に、皆が笑顔でいられるよう心を尽くし
ていかなければと、涅槃図の前で心新たにしたひと時で
した。
戻る***2024/02/21~29 無縄自縛 [#y4a79224]
講師:愛媛県 晴光院 曽根隆弘師
先日、今年四十歳になる友人と会った時のことです。少
しうんざりした様子で「最近よく、結婚しないの?と聞
かれるようになって…」と、話しだしました。「それは
先々のことを心配してくれているんじゃないのか?」と
私が応えると、「独身でいるのを寂しいものだと決めつ
けられても困るんだよ。親や親戚が心配して言うのなら
まだわかるけど、同級生や知り合いに言われてもなあ。
おれは今の生活で、リア充なんだよ。誰にも迷惑かけて
ないのだけどね」とぼやくのです。
ちなみにリア充とは、今時のSNSなどを通した仮の姿
ではなく、リアルな人間関係や趣味を通して人生を楽し
んでいること。「リアルが充実している」を略してリア
充と言います。
その友人とは「十人十色・百人百様・千差万別。人生百
年の時代には、結婚もさまざまな選択肢の中の一つとい
うことだね」とか「大人になったら結婚するものだとい
う固定観念をついつい口にしてしまう人も多いんだね」
などと話し、「またね」と別れたのですが、実は、少し
複雑な気持ちも残りました。
現代人は健康寿命が大幅に伸びました。科学技術の進歩
や価値観の多様化など、私たちをとりまく環境の変わり
ようは、昭和の時代とは比べ物になりません。人生の選
択肢も多くなりました。
社会人としての常識や人生観を持つことは大切ですが、
時としてそれが固定観念として柔軟な発想や適切な判断
力を妨げることがあります。私も昭和の時代の空気を浴
びて育った世代の一人です。気を付けていたつもりでも、
知らず知らずのうちに、さまざまな固定観念にとらわれ
てしまっているのではないだろうか?偏った常識やこだ
わりに縛られているのではないだろうか?複雑な気持ち
の正体は、自分自身への不安だったのかもしれません。
禅の教えに、無縄自縛(むじょうじばく)という言葉が
あります。自らを縛る縄など無いという四文字からなる
言葉は「あなたを縛っているのは、あなた自身である。
思い込みや先入観、執着や妄想を捨てなさい」と教えて
います。
人は年齢を重ねるにつれて、自分の考えが固定され、柔
軟さを失いがちです。しかし、「命を大切にすること」
「みんなと仲良くすること」「相手を思いやること」な
ど、人が生きる上で大切にしなければならない基本は変
わるものではありません。いかなる時も、誰に対しても、
自分の価値観を押し付けるのではなく、相手の立場を尊
重し、物事に柔軟に対応できるよう心がけたいものです
ね。
戻る***2024/02/11~20 満てる [#v1b00f48]
講師:高知県 予岳寺 濱田道圓師
私事ですが、高知県に移り住んで十七年目を迎えること
になりました。縁もゆかりもない土地でしたので、当初
は分からないことばかりでした。とりわけ、土地の古老
が話す土佐弁には随分悩まされました。幸いなことに齢
九十八を迎えた師匠は生粋の土佐人ですので、分からな
い言葉に出会う度に意味を教わり、今ではすっかり土佐
弁にも馴染みました。
そんな土佐弁に『みてる』という言葉があります。中国
地方では物が無くなるという意味で使われるそうなので
すが、土佐弁では主に、人が亡くなる、命が尽きるとい
う意味で使います。お寺にいますと、お檀家さんとの会
話で「〇〇がみてて何年なので法事を」とか「〇〇がみ
てたのでお葬式を」などと、日常的に使われる言葉です。
何気なく耳にし、口にしていたこの「みてる」という言
葉ですが、昨年、新聞を読んでいて、『みてる』は【満
足の「満」に「てる」と送り仮名をつけて】『満てる』
と書くのだと初めて知りました。亡くなった方が寿命を
全うした、満ち足りた人生であったというのが語源なの
だそうです。
私がこの法話の原稿を書いているのは、令和六年一月二
十日です。元日に発災した能登半島地震で被害に遭われ
た皆さまにお見舞い申し上げますとともに、お亡くなり
になられた方々のご冥福を心からお祈りいたします。
今年は、新型コロナが5類に移行して初めてのお正月で
した。御家族や親戚との久方ぶりの再会と団らんの最中
であったであろうにと思うと、本当に胸が痛みます。今
日午後2時の時点で犠牲者は232名との報道がありま
した。突然の災害で命を奪われたお一人お一人は『満て
た』といえるでしょうか? 満ち足りた人生であったの
でしょうか?命を全うしたと言えるでしょうか?そんな
はずはありませんね。到底納得できるわけがありません。
ところが、土佐弁では老若男女、その死因に関わらず、
人が亡くなれば『満てる』です。なぜ『満てる』なので
しょうか?
その答えは十人いれば十人の答えがあり、正解は無いの
かもしれません。それでもあえて、答えを出すとするな
らば…「満てるとは、亡くなった人が満ち足りたと満足
することではなく、見送る人が満たしてくれたと故人に
感謝することを満てるというのだ」と、私は思うのです。
そしてその「満てる」の感謝を、亡くなった人だけでは
なく、自分と関わる全ての人にも向け続け、『ありがと
う』と感謝する日々の先、長い眠りにつく瞬間にも『あ
りがとう』と思えたならば、送る人と送られる人が互い
に「満てる」と言える別れの日が来るのではないでしょ
うか。
いつ何時、何が起こるか分からないのがお互いの人生で
す。今日の一日、このひとときを丁寧に丁寧に、ありが
とうの言葉と共にすごしてまいりましょう。
2024/01/21~31 手のぬくもりに
講師:香川県 祥福寺 本山良宗師
一年を二十四の季節に分けた二十四節季では、今月二十
日から大寒とよばれる節季に入りました。大寒は各地で
大雪が降ったり一年の最低気温が記録されたりと、一年
でいちばん寒さが厳しくなる時季です。
私はこの時季になるとなぜか決まって「手袋を買いに」
というお話を思い出します。手袋を買いに?はて、どこ
かで聞いたことがあるような…と思った方もおられるの
ではないでしょうか?昭和二十九年から六十年近く、小
学三年生の国語の教科書に掲載されていたこともある、
新美南吉という方が書いた童話で、寒い冬の夜、手袋を
買いに人間の町に行く子狐と、子狐だけで行かせた母狐
の心情が描かれています。
このお話の冒頭、新美南吉は子を思う母親の愛情を、と
ても細やかな描写で表現しています。それは、初めて雪
を見た子狐が雪遊びに興じすぎて、すっかりかじかんで
しまった手を、母狐がやさしくあたためてあげるという
シーンです。
その部分を読んでみます『子狐は、「お母ちゃん、お手
々が冷たい、お手々がちんちんする」と言って、濡れて
牡丹色になった両手を母さん狐の前にさしだしました。
母さん狐は、その手に、はーっと息をふっかけて、ぬく
とい母さんの手でやんわり包んでやりながら、「もうす
ぐ暖くなるよ、雪をさわると、すぐ暖くなるもんだよ」
といいました』
いかがでしょうか。ほんの数行ですが、母親の気持ちが
じんわりと伝わってきます。雪遊びをした子どもの手は
どんなに冷たかったことでしょう。その冷たい手を迷う
ことなく自分の手にとり、やさしく包み込んで、温かい
息をはーっと吹きかけてあげる。読んでいるだけでその
情景が目に浮かんできて、自分の手まで温かくなるよう
な気がする素敵な文章です。
幼いころお母さんやお父さん、お婆ちゃんやお爺ちゃん
と手をつないで歩いたこと。あるいは大切な人と手と手
を重ねたこと。そんな思い出をお持ちではないでしょう
か?あの手のぬくもりをもう一度と思っても、「もうと
っくに亡くなっていて、ふれたくても、ふれてみようが
ない」という人もいることでしょう。
そのぬくもりを思い出したいときは、亡き人を偲んで静
かに目を閉じ、そっと手を合わせ、しばらくそのままで
いてみてください。そうやっていると、合わせた手のぬ
くもりの中に、亡き人の手のぬくもりがよみがえってく
るような、おだやかな気持ちになれると思うのです。静
かに手を合わせるというのは、それだけで、手のぬくも
りだけでなく、心の温かさまで思い出すことが出来る大
切な時間なのですね。
もし、一緒に外歩きをするような小さいお子さんやお孫
さんがいらっしゃるようであれば、手のぬくもりが伝わ
るようにやさしく握ってあげてください。小さな手がか
じかんでいるときは、やさしく包んで、はーッと温かい
息を吹きかけてあげてください。その感触、そのぬくも
りは大切な思い出となって、お子さんやお孫さんの心に
いつまでも残るはずです。
2024/01/11~20 鷺鶿(ろじ)雪に立つ
講師:愛媛県 晴光院 曽根隆光師
皆さんは大愚良寛という名のお坊さんをご存じでしょう
か?江戸時代を代表する禅僧で、親しみを込めて良寛さ
んと呼ばれる方です。良寛さんは若いころ、備中玉島、
現在の岡山県倉敷市にある円通寺という曹洞宗の修行道
場で坐禅三昧と托鉢の修行を二十年ほど続けた後、諸国
を巡って、晩年は越後国蒲原郡、現在の新潟県燕市の五
合庵という小さな庵に移り住み、生涯を仏道の修行者と
して慈悲行を貫かれた曹洞宗の僧侶です。
曹洞宗には良寛さまと題した御詠歌があります。その御
詠歌に「霞立つながき春日をこどもらと手まりつきつつ
この日暮らしつ」という一節があり、暖かな春の日に子
供たちと毬をつきながら一日を過ごす良寛さんの慈愛に
みちた情景が詠われています。
良寛さんはまた、詩人、歌人、とりわけ書家としても高
名な方で、その書風は一見つたなく、まるで素人が書い
たように感じられる、単純な細い線で書かれています。
しかしながら、そこには何ものにも囚われない自由さ、
おおらかさがあると言われ、現在でも多くのファンの心
を引き付けています。
何年か前、書道の先生に「私にも良寛さんのような字は
書けますか」とたずねたことがあります。すると先生は、
「良寛さんは、実は行書も草書も楷書もすべて練習して、
行き着いた先があの文字です。普通なら、良寛さんのよ
うな立派な僧侶には近づきがたいものですが、良寛さん
にはそういうところが全くなかったのでしょう。だから
こそ、大人のみならず年端もいかぬ子供たちにも愛され
て、一緒に毬つきをして遊んだりもできた。子どもは字
が、下手とか上手とか、字が曲がろうか、間違っていよ
うが、全く問題にしません。形や運筆が行き届かないと
ころがあっても、自分を正直に表します。良寛さんはそ
んな子どもたちの姿に心を打たれ、子どものように真率
な書を書こうとした。良寛さんの書はその素朴さと素直
さが表れた文字なのです」と話されました。
大本山總持寺をお開きになりました瑩山禅師さまは、禅
の心を『鷺鶿(ろじ)雪に立つ 同色(どうしょく)に
あらず』というお言葉で示されました。鷺鶿とは白鷺の
ことです。「雪の大地に降り立った真っ白な白鷺は、雪
の白を邪魔せず、そこに溶け込みながらも、白鷺として
の命を存分に謳歌している」と説かれたのです。白鷺は
周囲に溶け込んでいるのに、同時に、自分らしさも存分
に発揮している。相手の心も、自分の心も殺さない。禅
の生き方とは調和の心だと諭されました。
コロナ禍移行、レジハラというかカスハラという言葉を
よく聞くようになりました。レジハラとは、レジで店員
さんに大声で怒鳴ったりする振る舞い。カスハラとは企
業に理不尽なクレームをつけたりする行いのことをいう
のだそうです。私たちは、人によく見られたい、金も欲
しい、地位も欲しいと、やむことのない欲望に翻弄され
がちです。そしてそれが自分の思い通りにならない時、
その不満を誰かにぶつけようとします。コロナ禍のスト
レスで知らず知らずのうちにギスギスした心が蔓延した
結果が、レジハラやカスハラに顕れたといえるのかもし
れません。
良寛さんの書にファンが多いのは、その書を通して『鷺
鶿(ろじ)雪に立つ 同色(どうしょく)にあらず』と
いう、お互いを認め合う心をもつこと、思いやる心をも
つことが大切なのだ。禅の生き方、調和の心が大切なの
だと無言のうちに教えてくれているからではなのではな
いでしょうか。
『鷺鶿(ろじ)雪に立つ』の教えを心に刻んで、新しい
一年を歩んでまいりましょう。
2023/12/21~31 願い事の前に
講師:愛媛県 宗光寺 岡 芳樹 師
12月8日はお釈迦さまがお悟りに成られた日、成道会
です。この日に因み、私たちの町の仏教会では、我々の
曹洞宗だけでなく時宗や浄土真宗、華厳宗の和尚様方も
共に協力して「歳末助け合い托鉢」を修行致します。
宗派を越えて多くの和尚さんが集まると、托鉢の衣姿や
托鉢の方法、お唱えするお経も違います。宗旨も違えば
ご本尊も違います。けれども、私たちは、皆様から集め
られた浄財を生活の困っている方々や自然災害で被災さ
れた方々に届けたいという同じ思いをもって、駅前や商
店街を廻って托鉢をするのです。
この歳末助け合い托鉢の時期が来ると、私には必ず思い
出す言葉があります。それは、大学生の頃に出会ったあ
る海外の留学生の言葉です。彼は「日本の宗教はとても
素敵だね。日本の仏教には多くの宗派があり、神道やキ
リスト教を含め様々な宗教があるけれども、それぞれが
争う事がないのは素敵だよね」と、私に話してくれまし
た。
30年程前に耳にした時には「ふーん、そうなんだ」と
答えるくらいで、とりたてて深く考えることはありませ
んでした。しかし、ウクライナとロシア、イスラエルと
ガザの悲惨な報道を目にするたび、耳にするたびに、平
和な日々が過ごせているのは、とても有り難い事なのだ
と気づかされます。
宗派を越えて、宗教を越えて、誰しもが心から願うのは
平和な日常です。お釈迦さまがお悟りになられた「成道
会」の日に、無事に托鉢が出来ることを心から感謝して
今年も托鉢修行を終えることができました。
年の瀬もいよいよ押し迫りました。大晦日には除夜の鐘
を撞きにお寺に参られる方もおられることでしょう。神
社に初詣に向かわれる方もおられることでしょう。それ
ぞれにお願いごとをされるのでしょうけれど、私からひ
とつお願いがあります。それは何かというと、どうかご
自分の願い事の前に、世界が平和でありますように、み
んなが笑顔でいられますようにと、お祈りしていただき
たいのです。来る年が穏やかな一年となりますように。
2023/12/11~20 愛語 ~思いやる心~
講師:愛媛県 晴光院 曽根隆光師
「早く勉強しなさい」という言葉、お子さんのいる家庭
では合言葉のようになっているのではないでしょうか?
かく申す私もその一人です。息子が小学校一年生のとき、
国語の宿題がでているのに、いつまでもとりかかろうと
しないのを見てつい、「早くしなさい」と言ってしまい
ました。
彼は、私の言葉を聞いてしぶしぶ鉛筆を手に取って宿題
にとりかかったのですが、すぐに手遊びが始まりました。
私が再び「遊ぶのは後にして、先に宿題をやってしまい
なさい」と言うと、ゆっくりゆっくりと文字を書き始め
ましたので、やれやれと一息ついたのもつかの間、すぐ
にまた手遊びが始まってしまいました。
仕方がないので、消しゴムと鉛筆を机の上で戦わせてい
る姿を眺めていると、ようやく決着がついたようでした。
「で、どっちが勝ったの?」と尋ねると、彼は「消しゴ
ム。この前は鉛筆が勝ったから、今日は消しゴム」と、
答えました。「でもね、お父さん。最後には筆箱に帰っ
て仲良くするんだよ」と筆箱にしまいます。
いやいや、まだ勉強は終わってないだろと思いましたが、
そのときふと、私もよく親に宿題しなさいと言われ、同
じように消しゴムと鉛筆が戦っていたことを思い出しま
した。
私たちの世界は大人だけのものではありません。大人が
ルールを決め、そのルールを子どもたちも自然も社会も
共有しながら生活しています。しかし、子どもには子ど
もの視点があり、自然には自然の視点、社会には社会の
視点が存在します。私は自分の子どものころを思い出し
ながら、親が子どもに「早く勉強しなさい」と掛ける言
葉は、子どものためではなく、早く宿題を終わらせるこ
とで自分が解放されたいという、自分のための言葉だっ
たのではないか?と気づかされた瞬間でした。
私は、子どもの筆箱からそっと鉛筆と消しゴムを取り出
し「お父さんと一緒に宿題しよう」と、にこやかに語り
かけました。すると彼からは「うん!」と、元気のよい
答えが返ってきました。宿題がさくさくと進んだことは
申すまでもありません。
言葉は相手を励まし、心を軽やかにすることも出来ます
が、反対に深く相手を傷つけてしまうこともあります。
永平寺を開かれました道元禅師さまは、「正法眼蔵 菩
提薩埵四摂法」の中で「愛語は愛心よりおこる、愛心は
慈心を種子とせり」と説かれています。心のこもった言
葉をかけるには、まず自分が慈愛に満ちた心を持つこと
が必要であり、相手の成長と幸福を願って言葉をかける
ことが大切なのだとお示しです。
相手の立場に立って寄り添う心を養うこと。それが出来
た時、相手の心を思いやる言葉は相手だけではなく、自
分自身の生き方をも変えてくれるものなのではないでし
ょうか。
年の瀬を迎え、何かと慌ただしくなる時期です。こんな
ときこそ「愛語」。相手を思いやる心と言葉を失わない
よう気を付けて過ごしていきたいものですね。
[戻る>#navigator]]
2023/11/21~30 解き放たれる~行雲流水~
講師:香川県 南隆寺 大石光昭師
先日NHKで、10月に亡くなられた谷村新司さんを偲
んで、昨年の暮れに放送された「ザ・ヒューマン~谷村
新司~」が追悼番組として再放送されていました。その
中で谷村さんがこんなエピソードを語っておられました。
2004年、中国最高峰の音楽大学、上海音楽学院から
「音楽の心を教えられるのはあなたしかいない。是非教
授に就任して戴きたい。」という依頼が舞い込んだそう
です。
その、上海音楽学院での初授業で谷村さんは、水を半分
入れたコップを見て詩を書いてもらうという授業をされ
ました。当時の学生たちは、古典音楽を学ぶばかりで作
詞は一度もしたことがなかったそうです。ほとんどの学
生が「コップの中に水が入っています」としか表現しな
い中で、ある二人の詩だけが違っていたというのです。
それは次のようなものでした。
一人は「コップが倒れて水がこぼれました。水は初めて
自由を知りました」。もう一人は「コップが倒れて水が
こぼれました。水は自分の形が分りませんでした」。コ
ップが倒れてこぼれた水が初めて自由を知る。自分には
形が無いことを知る。谷村新司さんはこの二つの詩の発
想の素晴らしさと表現力に鳥肌が立ったそうです。
そういえば以前、谷村さんは1980年に発表された、
ご自身の代表作ともいえる「昴」を回顧して、この詩で
最初に浮んだのは、最後の「さらば昴よ」という部分だ
ったとおっしゃってました。ご自分が作詞したにもかか
わらず、「なぜ、昴に別れを告げているのだろうか」と
いう疑問をずっと持ち続けておられたそうです。そして、
昴が発表されてから20年以上が過ぎた頃、「昴」とい
う星は、古代中国では「権力や財産の象徴」だったとい
うことを知ります。その時に初めて、「ああ、そうだっ
たのか。昴に別れを告げるのは、お金やモノ、物質的豊
かさを追い求めることに別れを告げよう、真の豊かさは
そこにはない。ということだったのか」と、気付かれた
のだそうです。
谷村新司さんの「昴」が国を越えて時を越えて、多くの
人に愛され続けているのは、その詞の中にご本人も気付
かないうちに、人間の身勝手な振る舞いを諫める大切な
教えが歌い込まれていたからなのですね。
このふたつのエピソードを考えるうちに、私の頭に「行
雲流水=こううんりゅうすい」という禅語が浮びました。
行雲流水、行く雲の如く流れる水の如し。空を行く雲は
立ちはだかる山を意に介すことなく通り過ぎ、流れる水
はきまった型を持たず、さえぎる岩を涼しい顔で通り過
ぎる。何事にもとらわれることのない心の大切さを教え
る言葉です。
止むことのない争いや環境破壊に明け暮れる私たち人間
の身勝手な振る舞い、それは全て昴という名の「モノ、
カネ、権威」という物差しにとらわれて、それに振り回
されているが故の行ないでありましょう。
谷村新司さんの「さらば昴よ」という歌声が聞こえてき
たら、谷村さんのメッセージとともに「行雲流水」とい
う言葉を思い出し、みずからの心と行いを振り返ってみ
てください。
[戻る>#navigator]]
2023/11/11~20 地球は大きな宝船
講師:香川県 南隆寺 大石光昭師
「アフターコロナの中で各地の秋祭りが4年ぶりに復活」
というニュースが報じられていますが、年回忌のご法事
も以前のように少しずつ賑やかさが戻ってきました。
そんな折のご法事で、読経を始めようとしましたら、床
の間に掛けてある赤いTシャツが目にとまりました。あ
のTシャツはいったい何だろう?「和尚は読経中にキョ
ロキョロしたり、ほか事を考えたりしているのか?」と
言われそうですが、何しろ床の間に赤いTシャツが床の
間に掛けてあるのです。しかも、左胸あたりには縦書き
で大きく「還暦」と書かれ、真ん中には宝船に乗った七
福神のイラストがプリントされているのです。「ああそ
うか、奥さんが還暦だったんだな。」
読経が終わって、私は冗談交じりに「いや~、お経中ず
っとあの赤いTシャツが気になって気になって」と言う
と、みんながどっと笑いました。すると奥さんが「この
小さい孫たちが、『じいちゃんが死んで、ばあちゃんが
寂しがっとるから、僕らが祝ってあげる』言うて贈って
くれたんですよ」と、少し目に涙をにじませて答えてく
ださいました。
そこで私は、Tシャツにプリントされている七福神の話
をすることにしました。「大黒さまや弁天さま、そして
毘沙門天はインドのヒンドゥー教の神さま、中国の布袋
さんは仏教のお坊さん、寿老人と福禄寿は中国道教の神
さま。そして、恵比寿さんは大漁や五穀豊穣・商売繁盛
の神で、唯一日本の神さまです。永平寺を開かれた道元
禅師さまは『仏道修行する者は一つの舟に乗って海を渡
るようなものだ。それは、水と乳がとけ合うように、心
を一つにしないといけない。』とおっしゃっておられま
す。仏教が伝わってくるのと一緒に、一つの舟にいろん
な神さまが次から次へと乗り込んで来たんですね。」と
言うと、小学生の女の子が間髪入れずに「せまい舟に喧
嘩せんと乗っとるな。仲よしなことが大事なんやなぁ」
私が「ええ~?○○ちゃんに一番ええところ全部取られ
たわ~」と言うと、再びどっと笑い声が起きました。す
ると、ご親戚のどなたかが「今日は、この家が宝船みた
いなもんや。じいちゃんも一緒に乗っとるわ」と言うと、
さっきの女の子がキョロキョロしながら「どこ?どこ?」
またまたみんなで大笑いしました。奥さんもその笑顔の
輪の中で、涙がこぼれないようにひと際大きく目を開い
て笑っておられました。
私たちが棲むこの地球も宝船と同じように、山河大地・
様々な国と地域・人種や宗教・動物と植物の分け隔てな
く、無数の生命を載せて回り続けてくれています。争い
や環境破壊に明け暮れる私たち人間の身勝手な振る舞い
によって、地球という宝船は大きく傾いて、今まさに難
破寸前なのではないでしょうか。
日々の行ないや言動を、仏さまやお祖師さま方のみ教え
に照らし合わせ、この素晴らしい地球が宝船として回り
続けられるよう努めてまいりましょう。
[戻る>#navigator]]
2023/10/21~31 喫茶喫飯
講師:愛媛県 晴光院 曽根隆弘師
私たちはとかく、仕事をしながらお茶を飲んだり、会議
をしながらコーヒーを飲んだり、食事をしながら仕事の
ことを考えたり、家族や友人との会話に夢中になったり。
いわゆる、ながら仕事といわれる、何かをしながら他の
ことをしたり、他のことを考えたりしてしまうことがあ
ります。
北海道のお寺にいた頃、近くのお檀家檀さんの家に命日
のお参りに伺ったときのことです。このお檀家さんは、
お参りの後いつもコーヒーを出してくれる方でした。
その日も、お参りが終わると、いつものように「おっさ
ん(お寺さん)、ありがとう。今、コーヒー出すから」
と、私に声をかけながら台所に入っていかれました。私
は、次のお参りの予定があるものの、コーヒーをだして
いただくのはいつもことですし、そんなに時間も掛から
ないだろうと思い「ありがとうございます」と、笑顔で
応えて待っていました。
しかし、その日に限ってなぜかコーヒーが出てきません。
「どうしたのかな?」と思っていると、台所からなにや
らカリカリと音が聞こえてくるのです。「あれ?もしか
して豆を挽いているのか?」といぶかしんでいると、今
度は、コポコポとお湯が沸くような音がしてきました。
しかしそれでもなお、コーヒーは出てきません。
次のお宅のお参りの時間が気になりだして、何度か時計
を見返しながらも、ありがとうございますといった手前、
次の予定があるのでもう結構ですとも言えません。私は
「これはもう、待つしかないな」と腹をくくって、時計
を見るのをあきらめました。その間、およそ二十分ほど
だったでしょうか、ようやく良い匂いと共にコーヒーが
出てきました。
一口飲むといつものコーヒーと、味が格段に違うのです。
コーヒーってこんなに美味しかったのかと感動しながら
「いつもいただくコーヒーと、豆の種類とか、淹れ方と
か、変えたんですか?」と尋ねると、その方は不思議な
顔で「いや、いつもと同じですよ。いつもはお経の間に
用意するんですが、今日はすっかり忘れてしまって、急
いで豆を挽いて淹れたんです」と仰るのです。
コーヒーを美味しくいただき、次のお檀家さんに向かう
道すがら、私は「同じコーヒー豆、同じ淹れ方なのに、
味がまったく違うように感じたのは、いったいどういう
ことなのだろう?」と自問自答しました。そして「そう
か、あの日以前の自分は、出していただいたコーヒーを
味わうよりも、次の予定を気にして、きちんと味わって
いなかったんだ」と気が付くと同時に、自分がいかに目
の前の事柄に集中していなかったのかと反省させられる、
味わい深い一杯のコーヒーでした。
大本山總持寺の御開山瑩山禅師さまに、喫茶喫飯【きっ
さきっぱん=茶(さ)に逢(お)うては茶を喫(きっ)
し、飯(はん)に逢うては飯を喫す】というお言葉があ
ります。『お茶を出されたときにはお茶をいただき、ご
飯を出されたときにはご飯をいただく』禅の教えとは、
決して特別な人が特別なことをすることではなく、誰も
が毎日を過ごす中で、その時その時の一つ一つに心を尽
くして丁寧に取り組むことだと示されました。
ゆっくりお茶を味わう時間を無くしてはいませんか?余
計なことを考えながらご飯を食べたりしていませんか?
そしてもちろん、「喫茶喫飯」はお茶やご飯をいただく
ときだけに限ったことではありません。仕事をする時は
目の前の仕事に打ち込む、勉強する時は学ぶべきことに
集中する。掃除する時、料理する時、日常生活のあらゆ
る場面に当てはまることですね。
せっかくの人生です。そのものの良さを、そのものの広
がりを楽しむ時間を持つためにも、今、自分がなすべき
ことに集中する。日常の生活のひとつひとつを丁寧に取
り組むよう、心がけてみませんか。
[戻る>#navigator]]
2023/09/21~30 禅的生活~学ぶはまねる
講師:徳島県 城満寺 田村航也師
禅宗といえば坐禅。禅寺の修行は明けても暮れても坐禅
ばかり・・と、思われがちですが、実は、生活のすべて
が修行であるというのが大切なところです。細かいとこ
ろまで厳格に定められている食事の作法や洗面の作法。
さらにはお風呂やお手洗いの作法に至るまでを、きちん
と身につけていくことが大事であると言われています。
なぜそんなに作法にこだわるのでしょうか?それは「お
釈迦さまのような生き方」というところに理由がありま
す。私が住職をしているお寺のご本尊さまはお釈迦さま
です。釈迦如来坐像と言って、坐禅の姿で坐っておられ
ます。お釈迦さまは坐禅の修行をされ、弟子たちにも坐
禅を勧めました。では、私たちがそのお釈迦さまを佛さ
まとして、本尊さまとして尊ぶのは坐禅をしているお釈
迦さまだけでしょうか?
そうではありませんね。お釈迦さまは、坐禅している時
ももちろん仏さまですが、立っていても坐っていても、
歩いていても横になっていても、いつであっても佛さま
です。ですから、お釈迦さまのように生きるには、坐禅
をしていない時もすべてお釈迦さまでなければならない
のです。そこで「禅宗の修行は坐禅だけでなく、生活の
すべてが修行」ということになってきます。
道元禅師さまも瑩山禅師さまも、禅寺生活の細かいとこ
ろまで、微に入り細に入り、懇切丁寧に教えておられま
す。本当の意味での親切です。それは、両禅師さまとも、
お釈迦さまのように生きたいと強く思っておられたから
です。
私は、道元禅師さまの、食事の作法を教える中のお言葉
が忘れられません。『お釈迦さまは食事の時に、お箸も
匙も使わず、手で食べておられた。だが、手で食べる作
法が伝わっていないので、仕方なくお箸と匙を使うのだ』
というお言葉です。道元禅師さまは、お釈迦さまの生活
すべてをまねることで、少しでもお釈迦さまの境地に近
づこうとお考えになったのですね。
「学ぶ」という言葉は一説に「まねる」→「まねぶ」→
「まなぶ」となったと言われております。皆さんも、日
々の生活の中で「これは素晴らしい、これは素敵だ」と
感じることに出会うことがおありだと思います。そんな
とき、それだけで終わらせるのではなく、ほんのわずか
なことだけでも真似をしてみてはいかがでしょうか?ど
んな小さなことでも、倦まずたゆまず積み重ねていくこ
とで、「これは素晴らしい、これは素敵だ」と感じたこ
とに近づくことが出来るはずです。
[戻る>#navigator]]
2023/08/21~31 自分の行いを顧みる
講師:愛媛県 宗光寺 岡 芳樹師
私が身につけたい習慣の一つに片付けがあります。実
は私、檀家さんや近所の方が目にするところの片付け
はきちんとできるのですが、自分の部屋などのプライ
ベートな場所の片付けが苦手です。
自分の部屋を片付ける時は、物を三つに分けるように
します。大切な物、まだ使える物、処分する物です。
まだ使える物は押し入れの奥や車庫などに押し込んで
いたのですが、先日ついに押し入れや車庫もいっぱい
になってしまいました。今までは処分すべきものは処
分して、残りは何処かに押し込んで、部屋の掃除を終
えていたのですが、ついに押し込む場所もなくなって
しまったのです。
そこで、妻の提案で、本や着なくなった服など、不用
なものを車いっぱいに詰め込んで、リサイクルショッ
プに持ち込みました。すべての物を買取査定してもら
い、値段がつかない物も全部引き取ってもらいました。
リサイクルショップからの帰路、私は妻に「リサイク
ルショップも遠かったし、町内のクリーンセンターで
全部処分してもらった方が良かったかな?」と言いま
した。すると妻は「私はそんなことないと思うけどね。
まだ使える物を捨てることのほうが嫌だし、今日引き
取ってもらった物は、また誰かが使ってくれるんだか
ら。」その言葉を聞いて私は、買取価格の低いことを
ずうっと気にしていた自分が恥ずかしくなりました。
道元禅師の教えの中に『脚下照顧』という言葉があり
ます。自分の足元を顧みて照らす。自分の行為を見つ
めなおして物事を行いなさいという意味です。自分の
損得ばかりを考えていると、自分の行為を顧みること
を忘れがちになります。
今回の一件では「物に溢れている時代とはいえ、物を
捨てるのは簡単ではない」ということに気づかされま
した。そしてもうひとつ気づかされたのは「物を買う
ときには、本当に必要なものなのかどうかを吟味して
物を買い、それが不要になったときには安易に捨てる
のではなく、それを使ってくれる人はいないか?それ
を他に利用する手立てはないか?と、もう一度自分の
行いを顧みなければ、本当に使い切ったとは言えない」
ということです。
それぞれの行動を起こすときにはまず『脚下照顧』。
自分を見つめなおしてみることが大切ですね。
[戻る>#navigator]]
2023/08/11~20 不殺生戒
講師:愛媛県 宗光寺 岡 芳樹師
私の長男はこの夏で四歳になります。蝉やバッタ、トン
ボ、メダカやイモリなど、いろんな生き物に触れること
が大好きで、夕方まで近所で虫捕りやサワガニ捕りをし
ています。幼稚園から帰るとすぐに私のところに来て虫
を捕りに行こうと言います。
幼児期に草花や小さな生き物に触れるという体験は、豊
かな感受性の発達をうながすといわれているそうですか
ら、なるべく長男の求めに応じるようにしているのです
が・・・。実は私、子供の頃に多くのカブトムシを捕ま
えて飼ってはみたものの、世話をしなかったせいでそれ
らのカブトムシを死なせてしまったという苦い経験があ
ります。
虫捕りをすると、どうしてもそのときのことが頭をよぎ
って、虫捕りで捕まえた虫たちにとっては、ひと夏の間
しか生きられない短い命なのに、それを無機質な虫かご
の中にとじこめて過ごさせるのということに、なんとも
いえない抵抗感を抱いてしまうのです。
仏の道を歩む上で最も基本的な教えに「不殺生戒」とい
う戒律があります。『むやみに生きとし生ける物の命を
そこなわず』という、自分の命はもちろんの事、自分以
外のあらゆる命あらゆる物を大切にせよという教えです。
私は、その教えを四歳の子どもにも分かりやすいように
伝えたうえで、飼い方のルールを決めてから虫捕りやサ
ワガニ捕りをすることにしました。そのルールとは、
一、トンボなどのように長生きしない昆虫はその日のう
ちに逃がすこと
一、魚のように生きる為の十分な環境を整えられない生
き物はその日のうちに逃がすこと
一、イモリやサワガニも家族がいるはずだから二泊三日
でいったん帰省させてあげること
以上の三つの約束です。
この虫捕りのルールを決めたことで私の気持ちも軽くな
り、一緒に虫捕りを楽しめるようになりました。捕まえ
た昆虫やサワガニ、イモリなども二泊三日の夕方には、
「ありがとうね。また遊ぼうね」って言ってお寺の庭や
近くの水路に逃がしてあげます。
生活の中に「不殺生戒」というひとつの戒律をとりいれ
ることで、私が嫌だった虫捕りも長男と一緒に心から楽
しめるようになりました。戒律を守るということは、自
分の生活を縛るためのものではなく、よりよく充実した
生活をさせてくれるものでもあるのですね。
[戻る>#navigator]]
2023/07/21~31 許す心 思いやる心
講師:愛媛県 宗安寺 能仁洋一師
いつもニコニコと和やかなお顔と柔らかなトーンでお話
しくださる方がいらっしゃいます。ここでは佐藤さんと
いたしましょうか。ご一緒にお話しをしていると、私の
心もとても穏やかにしていただける佐藤さん。
ある日、そんな佐藤さんからお話しいただいた内容に、
私は大変な衝撃を受けることになりました。それは数十
年も前に、佐藤さんご自身の子供さんが大変な事件に巻
き込まれ、そのことで佐藤さんは長年に亘り苦しんでこ
られた、そういったお話でした。
ある事件に巻き込まれた佐藤さんの子供さんは、なんと
犯人の手にかかり命を落とされてしまったそうです。大
切にしていた我が子を手にかけた犯人は、すぐに逮捕さ
れましたが、その犯人に対する佐藤さんの怒り憎しみは
相当なもので、「殺してやりたい!」と思うほどだった
そうです。
そして、その思いは、いつまでたっても消えることなく
月日が流れ、ふと気付くと身も心もボロボロになってい
る自分がそこにあったそうです。
佐藤さんが臨んだ、ある日の裁判でのことでした。出廷
してきた犯人の横顔はゲッソリとやつれており、今おか
れている状況に大変苦しんでいるように感じられたそう
です。その時佐藤さんは、「今まで犯人のことが、どう
しようもなく憎くて憎くて、なぜこんな苦しみを味合わ
されないといけないのかと恨みの中で生きてきた。けれ
ども、ああ、この人も、自分自信が犯してしまった罪に
よって、長年に亘って苦しんできたんだな」そんな思い
がよぎった時、ふと心の中で「もう、許そう」そう思っ
たのだそうです。
佐藤さんは犯人に対して「あなたは、私達の最愛の我が
子を手にかけるという、到底許すことなどできない罪を
犯した。しかし今、あなたの姿を見たときに、あなたは
あなたなりに自分が犯してしまった罪の重さにずっと苦
しんできたことが感じ取れた。そう感じた時に、きっと
我が子も、私達がいつまでも怒りや憎しみだけの人生を
送り続けることを臨んではいないだろうと思った。犯し
た罪は重いけれども、私はあなたを許します。これから
は、身体をいたわりながら、罪を償っていって欲しい」
そう言われたそうです。
それを聞いた犯人は、大粒の涙を流しながら佐藤さんに
対して頭を下げたということでした。
佐藤さんは話されます。「そのときまで私は、犯人に対
する怒りで我を忘れていたのだと思う。今思えば、犯人
を恨んだり憎んだりするのは精神的にも肉体的にも本当
に苦しかった。犯人を許そうと思った時に、その苦しみ
から解放されて、怒りと憎しみと共に、あの事件で時間
が止まっていた自分自身の心が、やっと前を向いて歩き
だせた。罪を犯したその犯人を許すことで、犯人の心も、
そして自分自身の心も救われたように思える」と。
大本山總持寺御開山瑩山禅師さまは『たとい難値難遇の
事有るも、必ず和合和睦の思いを生ずべし』と御示しに
なられ、人々の悲しみも苦悩も我が事のように受け止め
相和して生きる『同事』の教えをお説きになられました。
佐藤さんは自分自身大変な苦悩の中にありながらも、恨
み憎んでいた犯人の苦悩を感じとり、犯人の体をいたわ
る慈悲の心を向けられました。佐藤さんのとられた行動
は、まさに瑩山禅師様の『同事』の教えそのものだった
ように感じます。その慈悲の心は、今まで佐藤さんの心
の内にありながらも恨み憎しみが邪魔をして見えなくな
っていた『子供さんが佐藤さんの幸せを願う心』を照ら
し出し、犯人も佐藤さん自身も、そしてきっと子供さん
の心をも救ったのではないでしょうか。
それから数十年。佐藤さんは人と接する時、まずは相手
の立場に立ち、喜び・悲しみ・苦しみを我が事のように
受け止めながら相和して生きる『同事』を実践し続けて
こられたに違いありません。だからこそ声を荒げること
なく、いつもニコニコと和やかなお顔と柔らかな口調で
人と接することができるのだろうと思います。一朝一夕
に佐藤さんのようになることはできないでしょう。けれ
ども、『同事』の思いを心に持ち続けることはこの私に
も、そしてあなたにも出来るはずです。『同事』の思い
を心に持ち続け、やがて自然に行動に移せるよう、共々
に日々心がけてまいりましょう。
[戻る>#navigator]]
2023/07/11~20 一期一会
講師:愛媛県 宗安寺 能仁洋一師
午前6時に大梵鐘を鳴らし、その後、朝のおつとめをす
るのが日課になっています。昔は師匠である父が毎日や
っておりましたが、その父も昨年夏に85歳で遷化いた
しました。
父が最期を過ごしたのはショートステイ先の施設でした。
食が大変細くなり点滴の必要が出たため、介護タクシー
を頼んで二日おきにかかりつけの病院へ一緒に行き、施
設へと連れ帰る。そんな生活を一週間ほど続けました。
その日は金曜日、土日は病院が休診ということもあり、
「三日後の月曜日にまた迎えに来るけんね」と父に話し、
父の乗った車いすをスタッフさんに引き渡し、いつもの
ように父がエレベーターの扉の向こうに見えなくなるま
で見送っておりました。スタッフさんは仕事が忙しかっ
たのか、いつもなら私が立っている玄関が見えるように
方向転換をしてエレベーターに入っていくのに、その日
に限って方向転換をすることもなくそのままエレベータ
ーに乗り込み、父の後ろ姿が扉の向こうに消えていきま
した。何とも寂しい気持ちになりながらも『また三日後
に会えるから』と自分に言い聞かせ帰路につきました。
その二日後、父は旅立ちました。
病院の救急治療室で冷たくなった父に会い、あの日お互
い顔を見ながら送ってあげられなかったことの後悔と悲
しさが一気に胸に押し寄せてきました。会うたびに力が
衰え行く父を見ながら、いつ別れが来てもおかしくない
と、ほんのわずかな時間も無駄にはしないようにと大切
にしてきたのに、あの日、顔を合わせて見送ることが出
来なかった。そのことが、ただただ悔やまれて仕方がな
いのでした。
禅語に『一期一会』という言葉があります。これは『そ
の人と出会うこの瞬間は、一生にたった一度きりの、二
度と戻ることのない大切な時間なのですよ』という教え
です。
私は父の最期に接し、掛け替えのない大切な時間を共に
過ごしてまいりました。食事やお風呂、トイレや移動と
いった介護の数々。その当時はしんどいと思うこともあ
りましたが、振り返ってみますと、どれもが尊く有り難
い時間でした。しかし、『また三日後に会えるから』と
自分に言い聞かせながらも、父の背中しか見ることが出
来なかったあの瞬間。あの日あの時あの場所に戻って父
の顔を見たいと思っても、それは叶わぬことです。「あ
あ、この世は本当に無常なのだな」と思い、「必ず次が
あると思ってはいけない。今というこの瞬間は、二度と
は戻らない大切な時間なのだ」と再認識させられた父と
の別れでした。
家族と過ごす、友と過ごす、職場の同僚と過ごす、そん
ないつもと変わらない日常の時間。隣にいて過ごせるこ
ともあるでしょうし、遠方にいて電話越し、メール越し、
手紙越しで、お互いの思いを共有しながら過ごすことも
あるかと思います。距離がどれだけあろうとなかろうと、
相手を大切に思いやりながら過ごした時間は、お互いの
心と心が触れ合える、とても尊くかけがえのない大切な
時間です。
私たちの目の前に広がっている世界は、すべてが一期一
会の時間の連続でできています。そのことに気づき、目
の前のその時間を大切に過ごしていけるよう、共々に心
がけてまいりましょう。
[戻る>#navigator]]
2023/06/21~30 思いやり
講師 高知県 予岳寺 濱田道圓師
外国語に訳せない日本語というのがよく話題になります。
その一つに「すみません」の言葉があるそうです。
以前新聞に、浄土真宗の僧侶の方が出された本の一部が
掲載されておりました。そこには…私達日本人は「すみ
ません」を普段自然に多用しているので、海外に行った
日本人は「I’m sorry.」つまり「ごめんなさい」を連発
するそうです。その為、海外の方は、日本人はなぜそん
なに謝ってばかりなのかと、不思議に思うそうです。
その僧侶の方が仰るには、日本人が使う「すみません」
には時に応じて『謝罪』『感謝』『依頼』の意味合いが
あるとのこと。『謝罪』の「すみません」には、自らの
過ちを悔い、申し訳ないという気持ち。『感謝』の「す
みません」には、頂いたものや気持ちに十分なお礼が出
来ず申し訳ないという気持ち。『依頼』の「すみません」
には相手に何かしらの負担を掛けて申し訳ないという気
持ちが、それぞれ込められているのだそうです。
「すみません」は漢字で表しますと、サンズイに斉と書
く「済みません」が一般的です。自分の気持が収まらな
い、仕舞いがつかないという意味でしょう。他には、サ
ンズイに登るという漢字を用いて「澄みません」と書く
こともあるようです。これは、心中穏やかでなく、わだ
かまりのある状態ということでしょうか。
こうして見ると「すみません」の言葉には、どこからと
もなく込み上げてくる、相手を思いやる気持ちや、相手
への気遣いを感じますね。
この「すみません」という言葉には、相手への思いやり
が詰まっているのだと気付いたときに、私は道元禅師様
の『報謝を求めず唯単に利行に催おさるるなり』という
お言葉を思い出しました。「自分の損得を考えず、周り
の為に動きなさい」というお示しです。
自分の子どもや親戚の子どもがまだ小さかった頃のこと
を思い出してみてください。ヨチヨチ歩きの子どもが何
か転んだりすると「だいじょうぶ?」と、思わず腰を浮
かせ、声をかけたりしなかったでしょうか?2・3歳に
なって外遊びをするようになり、公園でかけっこをして
いた子どもが勢いよく転んだりしたら慌てて駆け寄って
怪我をしていないかと確かめたりしなかったでしょうか?
それと同じように、困っている人を見かけたら考える前
に「大丈夫ですか?」とひと声かける。倒れている人が
いれば駆け寄る。私は、この行動こそが道元禅師様の示
された生き方だと思うのです。ごく自然に、当たり前に
心配ができ、気遣いのできる思いやりと行動力を日々、
心がけてまいりましょう。
[戻る>#navigator]]
2023/06/11~20 ええこと聞いたわぁ
講師:高知県 予岳寺 濱田道圓師
聞く耳を持たないという言葉があります。相手の言うこ
とを聞く気がない、相手の言うことを聞かない、という
意味ですが、先日この言葉を改めて考え直すことがあり
ました。
木村祐一さんという方をご存知でしょうか?キム兄いと
も呼ばれる吉本興業所属のタレントさんで、NHKのテ
レビ番組『チコちゃんに叱られる!』でチコちゃんの声
を担当している人といえば、ああ、あの人かと思い当た
る方もおられるかもしれません。この木村さん、レシピ
本を出される程料理に精通されていて、料理愛好家とも
自称されているそうです。
先日、この木村さんがパーソナリティをつとめているラ
ジオ番組を聞いておりましたら、ある料理人の方をゲス
トにお迎えしていました。冒頭でゲストの方が、パスタ
料理のコツをほんの少し、ほんの数秒仰ったのですが、
すかさず木村さんは「そうなんですねぇ。ええこと聞い
たわぁ。」と漏らしたのです。
料理人と料理愛好家、料理という共通項があるにせよ、
ほんのちょっとした言葉も聞き逃さず、すかさず自分の
中に取り込もうとする木村さんの姿勢がラジオ越しに伝
わってきました。そのやりとりに感心しながら、反省し
たことがあります。
それは・・・自分は四十にして惑わずといわれる年を5
年も越えて、それなりの経験を積んできたと多少の自負
をしているが、その自負に慢心して、自分の経験を基準
にしたものの見方だけで、人と接してはいなかったか?
ということです。
道元禅師さまは「ただ我が身をも心をも放ち忘れて、仏
の家に投げ入れて、仏のかたより行われて~」というお
示しを遺されております。木村さんの「ええこと聞いた」
というひと言は、相手を尊重し、相手の話をよく聞こう
という木村さんの心がけがあればこそのひと言に違いあ
りません。
自分の考え方や、自分のやり方を前面に出すと、その感
情が邪魔をして、素直に自分の心に残したり、肝に銘じ
ることは出来なくなってしまいます。
自分の目の前にある、得難い知識や、教えを、自分の意
にそぐわないと見過ごすのは勿体無いことです。話をす
る側にしても、自分の話に真剣に耳を傾けてくれている
と思えば、その時間が心地良く感じられるはずです。
人と会うとき、人の話を聞くときには、自分の経験や感
情という壁を取り払って、真っさらな聞く耳、真っさら
な心の部屋を用意して臨むよう心掛けたいものですね。
[戻る>#navigator]]
2023/05/21~31 今なすべきことを
講師:香川県 南隆寺 大石光昭師
ある日の日曜坐禅会でのことです。坐禅の時間が終わり
茶話会に移ったとき、新しい参加者から、「坐禅中、い
ろんな思いが次から次へと浮んでくるのですが、皆さん
はどうしているんですか?」という質問がありました。
私がお茶を淹れながら少し間をとっていると「私も同じ
です。気にせず坐っています。」とか、「そやなぁ、調
子がええ時とそうでないときがあるなあ」とか、色々な
答えが出てきました。
それを受けて私が口を開こうとしたとき、それまで私と
同じように様子を見守っていたYさんが、「母親が入院
していたときに…」と話し出したのです。Yさんは坐禅
を始めて20年以上になる方です。その話はこうでした。
数年前、私(Yさん)は90歳になる母が急に体調を崩して
入院し、ふた月ほど坐禅会を休みました。いや、休んだ
というより、坐禅どころではなくなっていました。それ
は、母が退院したら家で介護をするのか?スロープや手
摺りなど家のリフォームをどうしようか?いやいや、施
設に入れてもらおうか?そもそも、その施設に空きはあ
るのか?等々いろんなことで思い悩んでのことです。
そして、いよいよ来週には退院という日の朝、目が覚め
た瞬間「あっ!今日は日曜日だ。久しぶりに南隆寺で坐
ってこよう」と思ったんです。そう思っただけで、なぜ
か少し心が軽くなりました。しかし、坐禅会で坐禅を組
んでみてもやはり同じでした。母の退院後のことで頭の
中は堂々めぐりです。
そんな時ふと、母の優しく笑う顔が浮んできました。そ
の瞬間、色々思い悩んでも仕方がない。今日は病院へ行
ってかあさんの顔でも見てこようと思い立ちました。す
ると、心のもやもやがスーッと晴れてすがすがしく坐れ
ました。
坐禅会が終わってその足で病院へ行くと、母はちょうど
朝食中でした。食べづらそうにしていたので、あれやこ
れやと手伝いながら食事を終えたときに、母は呂律が回
らないことばで「すまんなあ、ありがとう。あんたも忙
しいんやから、早よう帰りな」と息子の私を気遣ってく
れました。
そうこうしていると、日曜日だったにもかかわらず、な
ぜか主治医の先生が病室を覗いてくださって、私を見る
と先生は「ああYさん、今朝は早くから来られたんです
ねぇ。ちょうどよかったです。実は昨日、施設から連絡
があって、空きが一つ出来たそうですよ。」と言って、
次に母の方を向いて「Yさぁん、どうされますかぁ?い
れてもらいますかぁ?」と言うと、母は大きく頷いてく
れました。母に申し訳ないと思いながらも、私は本当に
胸をなで下ろしました…。
そのように話して、Yさんは最後に「手を組み、足を組
んで、仏さまと同じ形になった身体にやどる心からは、
間違った思いは生まれないのだと思います。」と付け加
えました。
自分ではどうしようもないことで悩んでもしょうがない、
取りあえず坐ってみよう、取りあえず母の顔を見てこよ
う。そのときできることをやればよい。Yさんは坐禅を
していてそう悟ったのだと思います。
お釈迦さまは『過去を追うな。未来を願うな。過去はす
でに捨てられた。そして未来はまだやって来ない。ただ
今日なすべきことを熱心になせ』とお示しになられてい
ます。過ぎ去ったことをクヨクヨ悔やまず、まだ来ない
先のことで取越し苦労をせず、今できることをせよとの
お諭しです。
禅の教えの根本は、姿勢を調え、呼吸を調え、心を調え
ることです。せめて一日に一度、ほんの数分でも心を調
える時間をもち、「いまここ、今日一日」を丁寧に過ご
すことを心がけてまいりましょう。
[戻る>#navigator]]
2023/05/11~20 布施の心を忘れずに
講師:香川県 南隆寺 大石光昭師
昭和60年夏、私が新居浜にある瑞應寺専門僧堂で修行中
のときのことです。当時の修行僧は折にふれて、楢崎富子
先生からお茶の手ほどきをいただいておりました。
梅雨直後のある暑い日の昼下がり、お茶室の前を通ると先
生が炎天下でゴザを広げ、汗だくになって炉の灰を仕立て
ておられました。私の顔を見ると先生は、番茶や丁子の煮
汁で「しめし灰」をつくることや、土用の暑いときにこそ
する作業だということなど、事細かくお教えくだいました。
そして最後に、「雲衲(修行僧)さんも檀務(ご法事など)に
行かれたら、『このお花は、おうちの方が丹精込めて活け
たものだとか、このお菓子は町の和菓子屋さんまで行って
吟味してくださったんだ』とか思わにゃいけんよ。お経読
んで、お茶飲んで、“ハイさよなら”じゃないんよ。人を
お迎えするということは、人知れず、いろんな準備や心遣
いがあるものなんよ。」と諭してくださいました。
それから何十年が経ち。恥ずかしながら、そのような出来
事などすっかり忘れていたある日のことです。月参りに伺
ったお檀家さんでお仏壇に向ったとき、なんだかいつもと
違う感じを抱きました。おばあちゃんの座る位置がいつも
と違うのです。そして、しきりに私の手元へ視線を集中さ
せているのです。どうしたんだろう?と思いつつ、お線香
を額のところで念じて立てたときに「ああ!これだったの
か!」と気が付きました。香炉の灰が綺麗になっていたの
です。先月までは、何回も抜いたり刺したりしないと立た
なかった線香が、その日はきれいにスッと立ちました。私
の手元に感じていた視線の先をたどると、おばあちゃんが
ニッコリと笑いかけてきました。私も笑顔で応えて、お経
を読みました。お経が終わると、おばあちゃんに「和尚さ
ん、気持ち良かったやろ?お線香立て」と聞かれたので、
先ほどのお茶の灰のお話しをしました。
するとおばあちゃんは「私、もう何十年も主人の命日に和
尚さんに来てもらいよっても、“お経はお経のプロに来て
もろうて読んでもらうんが一番”。ぐらいにしか思てなか
ったんです。でも昨日、お線香立てを掃除しよったら気持
ちがス~ッとして、『ああ!こうゆうことも、お茶菓子も、
お花も、何もかもひっくるめての月参りなんやなぁ』って、
今更ながらに気付いたんです。和尚さんゴメンなぁ」と。
私は「いえいえ、いつも本当によくしていただいておりま
す。ありがとうございます。」と感謝を申し上げました。
布施という言葉があります。布施とは相手を思いやる心で
す。炎天下での炉灰作りなどのお茶席の準備、お仏壇の香
炉の灰やお供えのお花などのご法事の準備も、相手に心地
よくすごしてもらおうという思いやりの発露であり、「布
施の心」が形として表れたものです。お釈迦さまや道元禅
師さまの「布施」の御教えが、途切れることなく連綿と伝
わってきたことを思うと、有り難さが身に染みてまいりま
す。
新型コロナの位置づけが5類に移行し、私たちの日常もコ
ロナ以前に戻ろうとしています。外出時にマスクを着けず
に歩く人を見かけるようになりました。その一方で、ご高
齢の方、重症化リスクの高い方々にとって安心できない状
況であることに変わりはありません。お茶事やご法事だけ
でなく、日々のすべての行いに、布施の心、相手を思いや
る心を忘れぬよう、心がけてまいりましょう。
[戻る>#navigator]]
2023/04/21~30 他は是れ吾にあらず
講師:高知県 浄貞寺 伊藤正賢師
春爛漫の四月、心がウキウキする季節です。新入学生、
新社会人と成られた方もおられることと思います。そし
て、それ以外の方にとっても四月は年度替わりの月であ
り、転勤や移動などで、新人気分を味わっている方も多
いことでありましょう。
かく言う私にも、新人と呼ばれる時代がありました。か
れこれ四十数年前の三月、私は大学を卒業して修行道場
の門を叩きました。新入社員ならば会社の新入社員研修
を受ける頃だと思います。姿形と日数などの違いはあり
ますが、私共宗侶にとっての新入社員研修が「修行道場
への入門」だといえるかもしれません。
会社員生活をしたことがありませんので何とも言えませ
んが、修行道場の生活では、最初の三か月が最も辛い期
間でした。色々なことを教わるのですが、「尊公そんな
ことも知らないのか?…尊公というのは君、といった意
味です…尊公それで良く、この本山に来られたもんだ」
と言われたり、「尊公そんなことも出来ないのか?尊公
の師匠は、いったい何を教えてくれたのだ?」と、手厳
しく言われたり、キツく指導されたこともありました。
先輩に対して面と向かって口に出せるはずもなく、「我
が師匠の事を知らないアンタに、そこまで酷く師匠のこ
とを言われたくは無いわ」と思いながら、ジッと耐え忍
ぶしかありませんでした。
ならぬ堪忍するが堪忍とはこういうことだ。殆どの修行
僧が言われたり、されたりしてきたことだと辛抱しなが
ら、体が覚えて自然にできるようになるまで、ひたすら
目の前のことに打ち込む日々。今になれば、理屈や知識
ではなく実践することによってはじめて得られるものが
あるのだと教わった三か月でありました。
上山して三か月が過ぎ、ようやく体も神経も修行生活に
慣れて来た頃でした。ある修行僧の先輩が私に「正賢和
尚、こんな言葉を聞いたことあるかい?」と語りかけて
くれました。「それはな、道元禅師さまが書かれた典座
教訓(てんぞきょうくん)という書物の中にある『他は
是れ吾にあらず』という言葉だ。修行は自分が自分です
るものだ、他の誰でもなく自分自身が経験して会得しな
ければ意味がないというお示しだ。お前さんは、つい数
か月前まで学生だったよね?大学生活も試験やら生活費
の工面やらと、それなりに大変な事もあっただろうけれ
ど、本山の修行の大変さは比べ物にならないだろ?いろ
んな事を覚えなければならないし、苦しい事も多いだろ?
だけどな、周りの先輩方もみな通ってきた道だ、早く一
人前の修行僧になって欲しいから厳しくしているんだよ
…分かるかな?それが『他は是れ吾にあらず』だ。道元
禅師さまが、七百年の時を越えて我々に教えてくださっ
ているんだよ。この言葉には続きがあってな『更に何れ
の時をか待たん』とお示しだ。つまり、後でやろうなど
と思うな。わずかな時間も無駄にするなよと。道元禅師
さまが優しくも厳しく諭して下さっているんだよ。」と、
教えて下さったのです。修行生活はそれからも大変なこ
とばかりでしたが、その先輩の言葉のおかげで一年間の
修行生活を無事に終えることが出来ました。
いま、新しい環境の中で様々な壁にぶつかっている方も
いるのではないでしょうか?与えられた課題が出来るか
どうか?不安にかられている方もいるかもしれません。
まずは、やってみましょう。『他は是れ吾にあらず、更
に何れの時をか待たん』です。
[戻る>#navigator]]
2023/04/11~20 肌色のクレヨン
講師:愛媛県 法蓮寺 川本哲志師
皆さんは最近のクレヨンや色鉛筆に「肌色」が無いこと
をご存知だったでしょうか?小学生の娘がクレヨンで色
塗りをしていた時のことです。娘に「ここは肌色で塗っ
てみたらどうだい?」と私が言うと、「肌色ってどんな
色?そんな名前の色はないよ」と言われました。一昔前
の「肌色」は、今は「うすだいだい」や「ペールオレン
ジ」という色名に変わっていました。
私が子供のころ、文字通り肌の色としてクレヨンに入っ
ていた肌色という色の表記は「人の肌の色というのはこ
ういう色なのだ」という固定観念を与える可能性がある
として、大手文具メーカー各社は2000年頃から使わなく
なったのだそうです。
国際化が進む中で、日本においても様々な肌の色の人た
ちが暮らすようになりました。日本で教育を受ける外国
の子どもが、肌色と表記されたクレヨンを手にしたとき、
「自分の肌と違う」と感じるのは、けして好ましいこと
ではないですね。肌の色に特定の色を定義付けすること
は複雑な誤解を招き、差別的な認識を拡大することにも
なりかねません。私たちが気づこうとしなかっただけで、
クレヨンの中に「肌色」が当たり前にあった時代に、つ
らい思いをしていた人がいたにちがいありません。
多様性という言葉が社会で叫ばれるようになった現代に
おいて、様々な立場を理解し、認め合い、受け入れ、支
え合っていくことはとても大切なことです。人種や国籍、
あるいは年齢や育ってきた環境によって「普通」や「当
たり前」の感覚は様々です。これからの未来を生きる子
ども達にとって「肌の色はこの色」と意識付けされない
ようにする配慮は、多様性を重んじる教育の第一歩とい
えるかもしれません。
『同事』という禅語があります。事を同じくすると書き
「相手と同じ立場になって思いやり、行動する」ことを
意味します。肌の色が違う人と出会った時、私たちは瞬
間的に「この人は日本人ではない」と判別してしまいが
ちです。しかし、肌の色だけで日本人かどうかが決まる
わけではありません。肌の色が違うという区別が、区別
の枠を超えて排他的になったり、差別的になったりする
ことがないよう、相手を理解すること、違いを受け入れ
ること、垣根を作らないこと。それが同事です。
クレヨンから肌色がなくなった一方で、肌色ばかりを集
めたクレヨンがあるそうです。世界の様々な肌の色がま
とめられていて、なかには40色セットの物もあり、肌色
といってもいろいろあることが分かります。多様性を理
解し、お互いを敬い、認め合う心を養ってまいりましょ
う。
[戻る>#navigator]]
2023/03/11~20 こだわりを捨てる
講師:愛媛県 晴光院 曽根隆弘師
小学校6年生の息子に、「なんで、学校では読み書きの
練習はするのに、聞く練習はしないの?」と、質問され
ました。「聞くことは、すべての基礎だからね」と答え
たのですが、何となく納得していない様子の息子を見な
がら、修行道場で共に修行に励んだ佐藤さんとの会話を
思い出しました。
佐藤さんは、私と同期の入門でしたが三歳年上で在家出
身。曹洞宗に限らず、色々なお寺で修行を積まれていて
独特の雰囲気があり、妙に馬が合って仲良くしてもらい
ました。
あるとき佐藤さんに、どんなお寺さんになりたいのかと、
尋ねたことがあります。すると「別に有名なお坊さんに
なりたいとも、立派なお坊さんになりたいとも思わない。
ただ、人の心に響く話ができるお坊さんになりたい。そ
れにはまず、いろんな人の話、とりわけ、目の前にいる
人の話をよく聞くことが大切だね。それは話すことにつ
ながる。相手と誠実に向き合うためにも、人々の悲しみ
の心に寄り添うためにも、聞くという学びが必要になっ
てくる。今はまだ分からんと思うから、いつか、そう言
っていた奴がいたなと思い出して」と、佐藤さんは話し
てくれました。
お釈迦さまは「まさに聞思修(もんししゅ)の慧(え)
をもって、しかも自ら増益(ぞうやく)すべし」と、お
示しになられています。
「聞」とは、人の話をよく聞くということ。固定観念に
とらわれず、素直な心で人の話に耳を傾け、相手を理解
することです。
「思」とは、よく考えるということ。疑問や解らないと
ころがあれば、それについて人によく聞いて、よく調べ、
よく考えて、正しいことを求めていくことです。
「修」とは実践するということです。人の話をよく聞い
て、よく考えて、それを実践していくことです。
私たちの周りには、大なり小なり、必ず学びとなるもの
があります。その第一歩が「聞く」ことですね。人の話
を聞くというのは、何でもないことのようですが、自分
の都合の良いように聞くことはできても、相手の真意、
相手が自分に本当に伝えたいことを、間違いなく理解す
ることはなかなかできないものです。
今になって思えば、あのときの佐藤さんは、そのことを
私に伝えたかったのです。
何かに行き詰った時や、新しいことに挑戦する時、レベ
ルアップしたい時には、こうあるべきだとか、こうしな
ければならないといった、こだわりを捨てることが肝心
です。こだわりを捨てれば、よく聞き、よく考えること
が出来ます。こだわりを捨てれば、自分の視野が広くな
ります。その気づきを行動に移せた時、新しい出会いが
待っているはずです。四月は出会いの月と言います、こ
だわりを捨てることを心がけ、一歩を踏み出しましょう。
[戻る>#navigator]]
2023/03/11~20 柔軟心
講師:愛媛県 晴光院 曽根隆弘師
「狭い日本そんなに急いでどこに行く」という交通安全
標語を耳にしたことはありませんか?
学生時代の同級生、堀尾さんと一緒に徳島から愛媛に帰
ることになったときのことです。その時の運転手は私。
真夜中の道を雑談を交わしながら楽しく帰っていたので
すがスピードを出し過ぎていたのか「隆弘さん、そんな
に急がなくてもいいよ、そんなに急いでもあんまり時間
は変わらないから」と言われました。そして、それに続
けて彼は、母親との思い出話を聞かせてくれました。
彼は高校生のとき、交通事情により毎朝、母親に学校ま
で車で送ってもらっていたのだそうです。堀尾さんの母
親はマイペースな性格で、いくら学校に遅れそうだと言
ってもゆっくり走り、行けると思う信号でも用心して止
まる。いくら急いでと頼んでも、柳に風と言った顔で、
ゆっくり運転する母親にイライラして、文句ばかりの毎
日だったそうです。
ところがある日、黙って運転をしている母親を見ながら、
ハッと気が付いたのだそうです。運転している母親の姿
は、万一事故でも起こしたら大変なことになるからと、
用心のうえにも用心をしている姿だったのです。
それに気がついた堀尾さんは、送るのが嫌な日も、体調
が悪いときもあるはずなのに、文句一つ言わずに送って
くれる母親に、散々文句を言っている自分が恥ずかしく
なったそうです。そして、イライラしながら急いでも、
到着時間はあんまり違わないんだということにも気づい
たそうです。
それからは、イライラすることもなくなり、「母さん送
ってくれてありがとう」と感謝するようになったと、話
してくれました。
禅語に、柔軟心「にゅうなんしん」という言葉がありま
す。人の数だけ人の価値観があり、立場が変わればもの
の見方も違う。違いを受け入れ、尊重する柔らかな心を
持つ、という意味です。たとえ家族であっても、一人ひ
とり、それぞれの人生を歩んでいます。価値観も違えば、
目指していることや動機も違います。自己中心のひとり
よがりではなく、良いことも悪いことも、全てを受け入
れながら前に進むことが大切なのだという教えです。
堀尾さんは、母親の安全運転に徹する姿を見て、立場が
違えば物の見方や考え方も違うことに気づき、相手の気
持ちに寄り添い理解する柔軟心が生まれ、感謝する気持
ちが持てたのです。
その話を聞いて私が車のスピードを落とすと「あ、いや、
隆弘さん別にそこまでゆっくり走る必要はないと思うよ」
と笑顔で言われました。
皆さんは自分の価値観を押し付けようとして、声を荒げ
たことはありませんか?どうして分かってくれないんだ!
と、イライラしたことはありませんか?そんな時は柔軟
心……柔らかな心を心がけてください。
[戻る>#navigator]]
2023/02/21~28 相手の立場に立つ
講師:愛媛県 安楽寺 大井建人師
私たちの住む日本という国は、「諸外国に比べて比較的
差別が少ない国」だと認識している日本人が多く存在し
ますが、実状は全く違うとされています。例えば、男女
差別、障がい者差別、アイヌ民族や在日外国人の人権差
別などがあります。皆さんが思っている以上に、日本に
は多くの差別や人権問題が存在しているのです。
私は差別と聞くと、叔父が以前、発した言葉を思い出し
ます。
私の叔父の息子は先天性の身体障がい者で、手足の形が
よく知る形とは違った形をしています。私より10歳年上
で、小さい頃よく一緒に遊んでもらったのを覚えていま
す。
あれは、私が中学生の頃、叔父とテレビを見ていた時の
ことです。テレビでは、障がい者の子を持つ親にフォー
カスを当てた番組をしていました。その番組の出演者が、
「障がい者に対して、傍観者になっている人が多すぎる」
と発言した時、叔父はこう言ったのです。「障がい者、
障がい者と言うとるが、障がい者だって出来ないことば
かりやないわ。障がい者の子を持った人間が一番、その
子を障がい者と決めつけてるやないか。我が子は可哀想
だろう!と、親の自分は可哀想でしょ!と、叫んでいる
ようにしか聞こえん。同じ障がい者の子を持つ親として
悲しいわ!」私は叔父の言葉を聞いて、小さい頃、従弟
に遊んでもらった事を思い起こしました。従弟は、他の
人と同じように私と遊んでくれていました。私も従弟に
対して、他の人と同じように甘え、同じようにぶつかっ
ていっていました・・・。私は「そうだね、叔父さんの
言う通りだよ」と、言おうと思ったのですが、当事者で
ない自分に、それを言う資格は無いような気がして、結
局、一言も発することができませんでした。
しかし、『同事』という仏教の教えを知ったとき、あの
とき何も言わなかったことこそが、従弟を障がい者扱い
していたことに気がつきました。そして、それに気づき、
その考えや行いを改めていこうとすることが大切なのだ
と、気付かされました。
同事とは、事を同じくすると書いて同事です。相手の立
場に自分も立つという意味です。子どものころに「自分
がされて嫌なことは相手にもしちゃだめだよ。自分がさ
れて嫌なことは、相手だって嫌なことなんだから。」と
言われたことはないでしょうか?
私たちはとかく、障がい者の方がいると気を遣って特別
扱いをしてしまいます。その人が本当は出来ることであ
っても、できないと決めつけ、健常者とは別だと思って
しまいがちです。しかし、相手は、障がい者の方は、ど
う感じているでしょうか?本当はみんなと一緒に楽しみ
たい、みんなと一緒に何かをやって成功や失敗を体験し
てみたいと考えているかもしれません。
高齢者が電車で席を譲られて「年寄り扱いするんじゃな
い」と断って気まずい空気が流れることがあると聞きま
すが、それと同じで「障がい者という特別扱いをするん
じゃない」と思っている障がい者も、少なからずいるの
ではないでしょうか?
助けが必要な人とそうでない人、できる人とできない人、
人の心情は千差万別で、全てを汲み取るのは無理なこと
かもしれません。同事を成すということは難しいことで
すが、相手の立場になってみることを、常に心にとどめ
て忘れないようにしたものですね。
[戻る>#navigator]]
2023/02/11~20 守る
講師:高知県 予岳寺 濱田道圓師
先日、ご供養に向かう道すがら、ある交通安全標語が目
に留まりました。そこには、こう書かれていました。
『まもろうよ 交通ルールと ひとつのいのち』
私は、この標語を反芻しながら、ふと、違和感を覚えま
した。命はかけがえのないものですから「ひとつの命を
事故から守る」というのは、すんなり理解できます。し
かし、ふだん当たり前に使っている「ルールを守る」と
は、いったいどういうことなのだろう?という、言い回
しに対しての違和感でした。
お寺に帰り、早速『守』の漢字を調べてみますと『心に
たもつ・みさお・おさめる・その状態を維持する」とい
う意味がありました。なるほど、「ルールを守る」とい
うのはルールを心にしっかり刻み、そのルールに則った
状態を常に継続する、という意味なのかと納得すると同
時に、ある言葉が脳裏をよぎりました。
それは、お釈迦さまの最後の説法であります仏遺教経の
中の『不忘念』という言葉です。道元禅師さまは『守正
念』とも著しておられます。不忘念・守正念ともに「正
しい仏の教えを心にしっかり刻み、決して忘れないこと。
そう念ずる力が強ければ、自分自身の欲望に害われるこ
とはない」という教えです。
内閣府のデータによりますと、横断歩道でないところを
横断していた歩行者が交通事故で亡くなった原因の、実
に七割に法令違反があったそうです。
横断歩道を渡ると遠回りになるからと言って、横断禁止
の場所で道を渡ってしまうのは、少しでも楽をしたいと
いう小さな欲望と言えます。こっちは歩行者なんだから
とか、車が停まるべきだという気持ちは、小さな慢心と
言えます。その小さな欲望や慢心から、取り返しのつか
ない事故に繋がることも有り得るのです。先ほどの交通
標語の「まもろうよ…」という呼びかけは、運転してい
る人だけでなく、歩行者への呼びかけでもあるというこ
とですね。
そしてそれは、道路上だけでなく、人と人との繋がりの
中でも同じことが言えます。きまりやルールを無視して、
自分だけ楽をしようとしていると、周りから不信や反感
を買います。自己中心的な言動ばかりだと衝突も起きる
でしょう。
正しいのは何かを見極める。難しいことのようですが、
一旦立ち止まって、自分の心を落ち着けると、実は自ら
がその答えを知っているものです。仏の教えという物差
しを心にしっかり刻み、ひとりよがりの考え方に振り回
されぬよう、お互いを思いやる気持ちを忘れずに、毎日
を過ごしてまいりましょう。
[戻る>#navigator]]
2023/01/21~31 初志貫徹
講師:愛媛県 法蓮寺 川本哲志師
「少年式」という学校行事をご存知でしょうか?愛媛県だ
けで行われている行事のようですが、昔の成人に当たる元
服にちなみ、中学2年生の少年少女を対象にした、立志・
自覚・健康を願う式典です。内容は、講演を聞いたり合唱
をしたり奉仕活動をしたり、大人への一歩を踏み出すこと
の決意表明などを行ないます。
私の娘がその少年式を今年控えており、三十年前には私も
母校の中学校で経験しました。
娘には学校から、将来の志を立てる四字熟語を選定すると
いう宿題が出されていました。それも私の時と変わってお
らず、当時の私が選んだ四字熟語は「旗幟鮮明」でした。
主義主張や態度がはっきりしていることのたとえで、優柔
不断で頼りないと周囲から言われていた中学生の私は、そ
んな自分を変えようという目標を立てました。
当時と比べて自分はどれだけ成長できただろかと考えてみ
ると、「旗幟鮮明」の言葉は今なお私に必要な言葉だと感
じます。自分の考えや主張に自信が持てず、周囲の声や反
応を気にしがちなのは、中学生の頃から進歩していないな
と気付きました。
道元禅師のお言葉に『志至らざることは無常を思わざる故
なり』とあります。志が実現できないのは、人生の残され
た時間が刻々と減っていることを自覚できていないからだ、
という意味です。
誰もが命の保証を与えられていないにも関わらず、今日生
きているから明日も明後日も生きているだろうと考えます。
この錯覚が、志の実現に向けての心の甘さを生むのです。
子供の頃の夏休みが良い例です。休みに入ってすぐは、そ
の長い休みが永遠に続くかのような錯覚を覚え、面倒な宿
題などは後回しにしても大丈夫という気の緩みが生じます。
しかし、お盆が過ぎて残りの日数が少なくなると、「あと
何日」という緊張感が生まれ、この緊張感が後押しをして
難攻不落の宿題の山に取り組むことになります。
少年式に当たって、娘が選んだ四字熟語は「初志貫徹」で
した。親の思いを知ってか知らずか、初志貫徹という言葉
が私自身にも向けられているように感じました。
限りある命を自覚し、心に誓った志を貫き通せるように、
今という一瞬一瞬を大切に生きていきたいものです。
[戻る>#navigator]]
2023/01/11~20 お正月の過ごし方
講師:愛媛県 法蓮寺 川本哲志師
新年を迎え、早くも半月が過ぎようとしています。皆様
は令和五年の年明けをどのように過ごされたでしょうか。
お正月は歳神様が福を持って家を訪ねてくるとされてい
ます。門松や注連縄や鏡餅でお迎えした方も多いのでは
ないでしょうか。
正月三が日には歳神様を丁重にお迎えするためのしきた
りがあります。せっかく来ていただいた歳神様を払った
り流したりしないように、掃除や水仕事はやらないこと
とされています。炊事などの台所仕事も同じで、特に包
丁を使う行為は、物を切ることが歳神様との縁を切るこ
とを連想させるとして、お正月には縁起が悪いと言われ
ています。年末に大掃除を済ませておくことや、おせち
料理を事前に準備しておくことは、歳神様に失礼のない
ように気を配る風習だと言えるでしょう。
あまり知られていないことかもしれませんが、お正月に
は先祖が帰って来るとも言われています。もともと、先
祖を迎える行事は年に二回行われていて、お盆だけでな
く、お正月も先祖の魂をお迎えする行事でした。
鎌倉後期の随筆である徒然草には、「年の名残(中略)
亡き人のくる夜とて魂祭るわざは、このごろ都には無き
を、東の方には、なほする事にてありしこそ、あはれな
りしか」とあり、昔はお正月にもご先祖様を迎えて、共
に一年の幸せを願ったものとされていました。
コロナ禍で家族親戚が集まることが難しくなっています
が、懐かしいあの人が帰って来ると思えば、お迎えを疎
かにするわけにもいかず、一緒に新年を祝うのだと思え
ば、面倒に思えた年末の大掃除やおせち料理の準備もは
かどりそうです。
準備万端整えば、年の初めには忙しく家事をすることな
く、ゆっくりとお迎えすることができるでしょう。歳神
様やご先祖様を大事にすることに集中するお正月の風習
は、新年の健康や幸福を願う時間と心の余裕を、意識的
に作りだす知恵と言えるかもしれません。
今年もどうぞ、お健やかにお過ごしください。
[戻る>#navigator]]